※本記事にはPR広告が含まれています
「自分の意見を言いたいのに言えない」そんな悩みを抱える方はいませんか?

自分の意見をはっきり言うのって、結構勇気がいることですよね。
本記事では、次のような方に向けて、自分の意見が言えない原因と克服方法を解説します。
自分の意見が言えない背景には、心理的要因や環境的要因が複雑に絡み合っています。本記事では、自分の意見が言えない原因をわかりやすく解説し、解決に向けたステップをまとめました。
自分の意見が言えないことのリスクについても触れているので、当てはまる方はぜひ本記事の内容を参考に、少しずつ自分の意見を言う練習をしてみてはいかがでしょうか。

「自分の意見を言う」ことだけに限りませんが、少しずつ変わっていく自分に自信を感じられるはずです。
本記事のポイントは、次の通りです。
自分の意見を言えている?
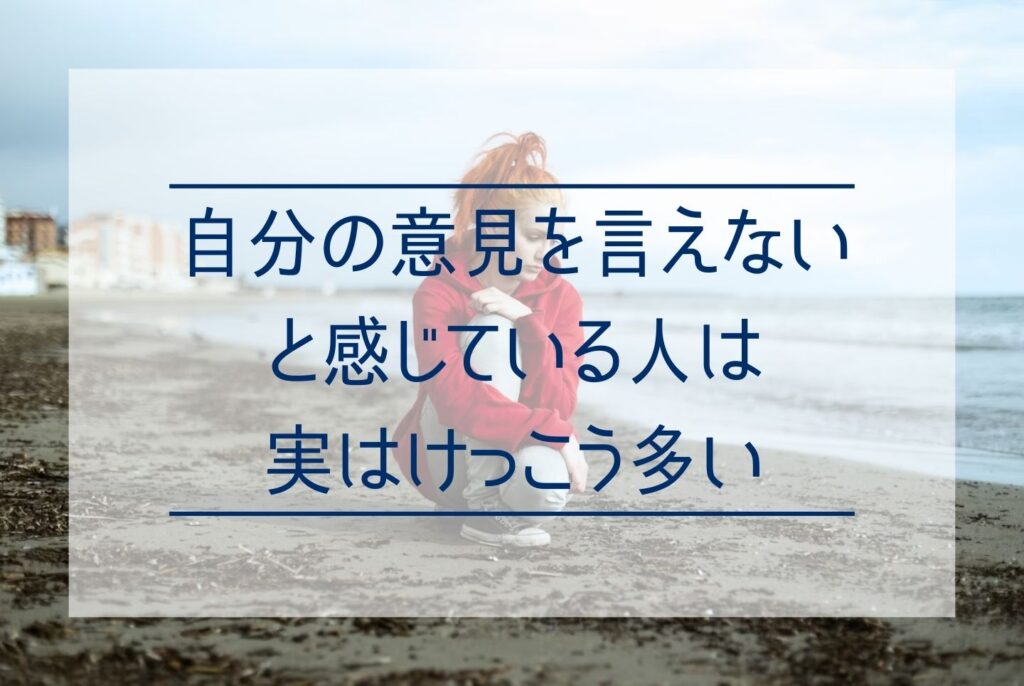
みなさんは、日々の生活のなかで自分の意見を言えているでしょうか?

うーん、言っている場面もある気がするけど、我慢していることのほうが多い気がする。
まずは、日常のなかで自分の意見を言えているかどうか、客観的に見てみましょう。「自分の意見が言えない」と感じていても、実際には意外と言えている場面もあるかもしれません。
会議での発言、友人との会話、家族とのやりとりなど、シーンごとに振り返ってみてください。どの場面で言えて、言えないのかを明確にすることが改善の第一歩です。

ちなみに、どれくらいの人が自分の意見や考えを言えているのか、参考となるデータもあります。
「(a)自分の考えや意見を積極的に表現する方だ」が43.1%,「(b)自分の考えや意見を表現することには消極的な方だ」が41.9%,「場合によると思う」が14.8%となっている。
引用元:文化庁|平成28年度「国語に関する世論調査」の結果の概要|4ページ(最終閲覧日2025年8月20日)
少し前のデータになりますが、「自分の考えを積極的に言えている」と感じている人は、それほど多くないといえるでしょう。
自分の意見を言えない原因・理由【心理面・環境面】
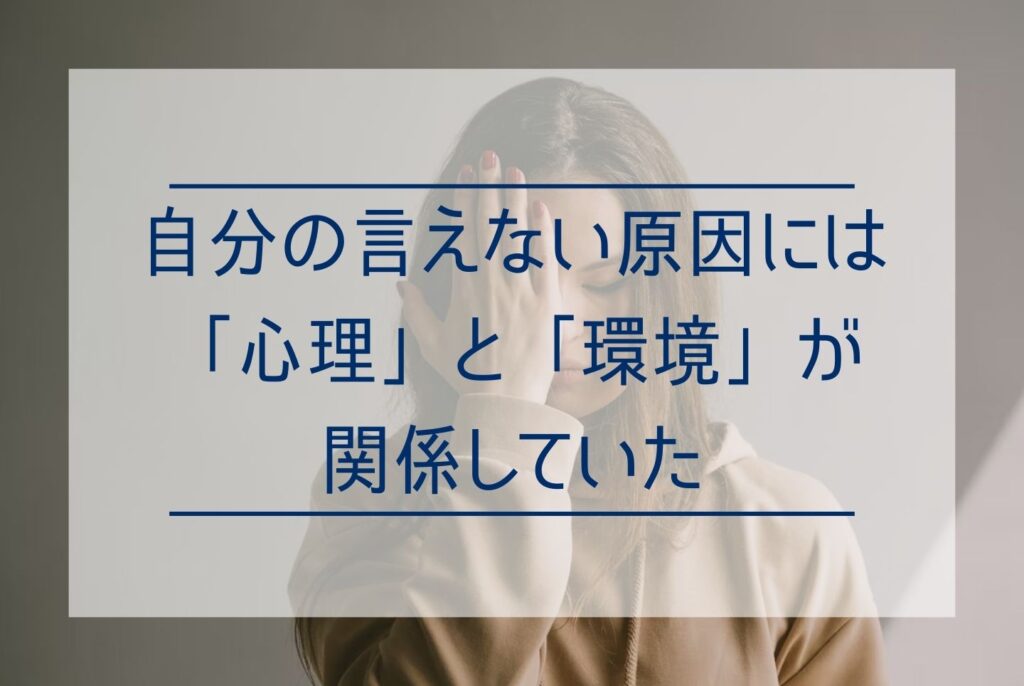
自分の意見が言えない原因は、大きく「心理面」と「環境面」の2つに分けられます。自分がどのような要因に当てはまるかを知ることで、改善策を見つけやすくなるはずです。ここでは、自分の意見を言えない原因を、心理面と環境面の両方から見ていきます。
【心理面】自分の意見・考えを言えない理由
自分の意見が言えない理由には、自分自身の心理的な要因があります。複数の心理的要因が組み合って、自分の意見が言えなくなってしまうのです。以下の項目で、自分に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
間違えたり否定されたりしたくない
「間違ったことを言って恥をかくかもしれない」「否定されて傷つくかもしれない」という不安から、発言を控えてしまうケースです。完璧を求めすぎる傾向があり、100%正しいと確信できないと発言できません。

僕は社会人になりたての頃、「こんなこともわからないの?」と思われたくなくて、なかなか思っていることを質問できませんでした。
本来、議論や会話は間違いを恐れずに参加することで成立するものです。ただ、完璧主義的な傾向があると、なかなか自分の意見を言いづらくなってしまいます。
自己肯定感が低く、自分に自信がない
「自分の考えなんて価値がない」「こんなことを言っても相手にされない」と感じてしまう状態です。自己肯定感の低さが根本的な原因となり、自分の意見に価値を見出せません。

実は良いアイディアかもしれないのに、「どうせ」という気持ちが先立ってしまうんですよね。
自己肯定感が低いと、自分の意見が正しいと信じにくく、意見を言う不安が強くなってしまいます。防衛的になり、意見を表明することがむずかしくなるのです。
他人に嫌われたくない
人間関係を維持したい気持ちが強すぎて、波風を立てるかもしれない発言を避けてしまいます。特に繊細な人ほど相手の反応を敏感に察知し、嫌われるリスクを避けようとします。

無意識に本音をおさえこんでしまっているのが怖いですよね。めっちゃわかります…
しかし、本音を隠し続けることは、逆に関係性を浅くしてしまう可能性があります。本音を隠すことで、相手とのやり取りが表面的で建前上のものばかりになり、結局は他社との関係が深まりづらくなるのです。
相手や場の空気を乱したくない
日本の文化的背景もあり、和を重んじるあまり自分の意見を控える傾向があります。

あくまでも通説で、確証はありませんが、なるべく場を乱したくないと感じる人は多いですよね。
会議で反対意見を言いにくい、グループの雰囲気を壊したくないという気持ちが強く働きます。
「こころ優しい」日本人は、言葉にせよ、態度にせよ、自分を積極的に他者に対峙させること自体、とかく攻撃的なので良くないと捉える傾向が強いのではないでしょうか。
引用元:PRESIDENT Online|日本の会議はなぜ”独り言大会”になるのか(最終閲覧日2025年8月20日)

“全会一致”という概念は、欧米では違和感があるようです。確かに、反対の人がいてもおかしくないですよね。
本来、建設的な意見交換こそが良い結果を生む場合も多く、自分の意見の適切な伝え方を身につけることが重要です。
過去の否定や失敗体験
子どもの頃に、発言して恥をかいた経験などが影響している場合もあります。一度の失敗体験が強く印象に残り、発言することへの恐怖心を抱き続けているケースです。

子どもの頃、簡単なことに失敗すると「恥ずかしさ」を感じるという研究もあるようです。
「困難な取り組み」に失敗した場合よりも、「簡単な取り組み」に失敗した場合に有意に多くの「恥ずかしさ」が示され、被検者が困難な取り組みに成功した場合に有意に多くの「誇り」が示されている。
引用元:橘 和代,杉浦 宏季,真田悦子|『保育』・教育実習において学生が自己評価する表現実技における羞恥心の実態|2019(最終閲覧日2025年8月20日)

確かに、「みんながわかっていること」を間違えたときの恥ずかしさは、尋常じゃないですよね。
自分の意見を言えるようになるには、過去の体験と現在の状況は異なることを理解することが第一歩となります。
注目されたくない
人前で話すことで注目を集めることに抵抗感を持つタイプです。内向的な性格の人に多く見られ、目立つことを好まない傾向があります。小さな集団では話せても、大勢の前では緊張してしまいます。
ただ、自分の意見を言うことを控えて、注目を避けることは、精神的安全性を守る行為でもあります。必ずしも悪いこととはいえないことも、覚えておきましょう。
精神的健康を促進する影響をもつ発言抑制の側面が存在する
引用元:畑中美穂|『会話場面における発言の抑制が精神的健康に及ぼす影響』|2003(最終閲覧日2025年8月20日)

自分の意見を言うことで、ストレスがたまってしまう場合もありますからね。
段階的に慣れて、徐々に人前での発言に対する抵抗感を減らしていくことが大切です。
責任を回避したい
発言することで責任を負うことを避けたい心理が働いています。「意見を言って、もしその通りにならなかったら責められる」という恐れから、あえて発言しない選択をしてしまいます。

確かに、意見を言ったら「じゃあ責任とって」ってなりかねませんもんね。それは受け取る側の問題でもある気がしますが…
意見を言うことと責任を負うことは必ずしも直結しませんが、どうしても抵抗感が生まれて、自分の考えを言えなくなってしまうのです。
【環境面】自分の意見・考えを言えない理由
環境面の原因は、周囲の状況や文化的背景によって「自分の意見が言えない」状態が作られているケースです。個人の努力だけでは変えにくい外的要因が多いため、まずは現在の環境を客観的に分析することから始めましょう。
環境面における、自分の意見や考えを言えない理由は次の通りです。
厳しいしつけや親に否定される家庭環境
幼少期から「子どもは黙っていなさい」「余計なことを言うな」といった否定的な言葉を聞いて育つと、自分の意見を表現することへの恐怖心が根深く残ります。否定される環境で育つと、次のような心理的なメカニズムがはたらきます。
| 心理的メカニズム | 内容 |
| 自己肯定感・自己信頼感の低下 | 自己否定的な思い込みが形成され、自分の意見や気持ちを安心して外に出せない。 |
| 発言への否定的な経験(条件付け) | 「話す=怒られる・否定される」という経験が刷り込まれ、意見を言うことに恐怖や危険を感じる。 |
| 安全基地の喪失 | ありのままの自分を受け入れてもらえないことで、感情や考えを表現することが「安全ではない」と学習する。 |
| 社会的スキルの発達阻害 | 幼少期に自分の意見を言う経験ができないと、成長してからも不安や恐怖を感じる。 |

良くも悪くも無意識や価値観は、子どもの頃に形成されるっていいますからね。
親の価値観や教育方針が強く影響し、大人になっても「発言してはいけない」という思い込みが続いてしまいます。厳しいしつけをされて育った人は、特に意識的な改善が必要です。
発言が認められない、受け入れられない雰囲気
職場や学校、地域コミュニティで、発言しても軽視される、無視される、批判されるといった経験が続くと、しだいに発言意欲を失ってしまいます。次のような年功序列が強い組織や、既存の考え方に固執する環境では、新しい意見や若い世代の声が届きにくくなります。

誰でも意見を言える環境って、本当は組織の成長のために重要なんですけどね。若かったり経験が浅かったりすると、どうしても発言しづらいですよね。
日常的な職場・学校・家庭・地域社会のなかでも、自分の意見が言いにくい状況は少なくないでしょう。
集団内の同調圧力の強さ
「みんなと同じでないといけない」という圧力が強い環境では、異なる意見を言いづらくなります。

みんなと同じじゃなきゃ不安になる気持ち、わかります。原始時代から、「仲間から外されないように」っていう本能があったと聞いたことがありあります。
個人が集団に所属できなければ、安全に生存できないということが言えるのである。その集団に必然的に所属する必要は同調の基だと考えている。
引用元:アダム マンスル|現代社会の同調圧力についての一考察 -行動させる社会-|5ページ(最終閲覧日2025年8月21日)
特に田舎や小さなコミュニティほど、周囲との協調を重視する傾向があり、目立つ発言は避けられがちです。同調圧力は無意識のうちに働くため、自分では気づきにくい環境要因のひとつです。
「我慢は美徳」という文化的背景
日本の伝統的な価値観では、自分の主張を控えめにすることが美徳とされてきました。「出る杭は打たれる」「沈黙は金」といった言葉に表れるように、積極的な自己主張は好まれない文化があります。
自己主張せず、言わず語らずのうちにお互いの気持ちが分かり合う「以心伝心」が日本社会の一つの特徴だと言えるだろう。
引用元:許 恵玉|「日本文化」と「中国文化」のイメージ比較研究-日本人のマインドマップ調査による検討-|4ページ(最終閲覧日2025年8月21日)

日本では「調和を乱さない」といった、他者への配慮が文化としてある感じがします。
日本の文化的背景が、現代でも多くの人が自分の意見を言いにくくなる要因となっているといえます。
自分の意見を言えないことのリスク・デメリット
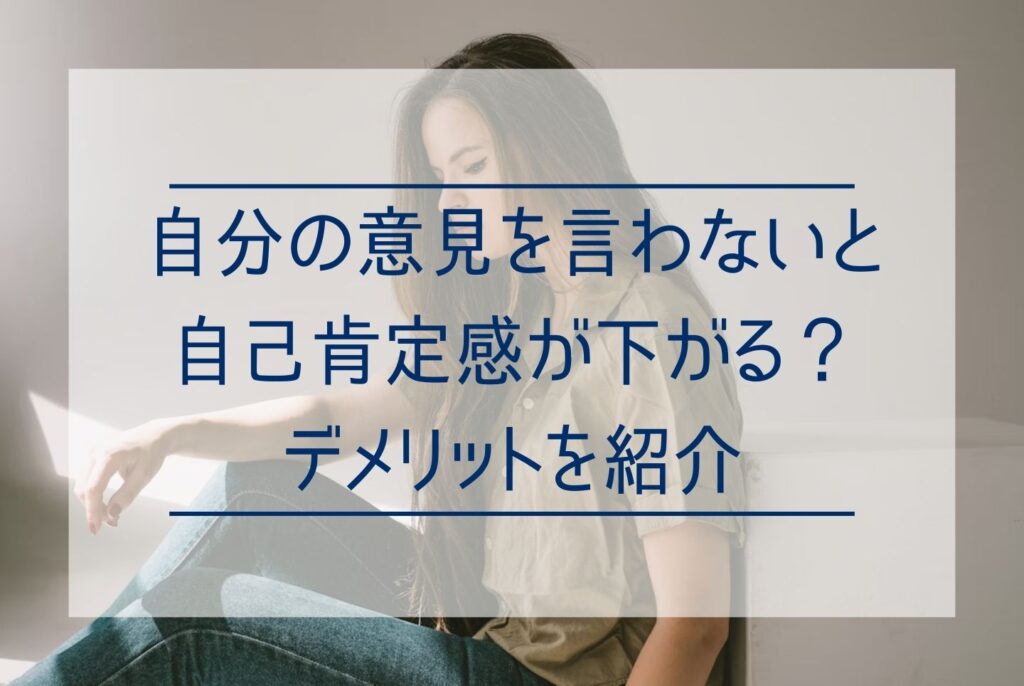
自分の意見が言えないことは、一見すると衝突や問題を避けられる安全な選択に思えるかもしれません。しかし実際には、個人にとっても組織にとっても、大きなデメリットをもたらします。ここでは見過ごされがちなリスクを詳しく見ていきましょう。
自分の意見を言えないことのリスクやデメリットは、次の通りです。
ストレスや不満を抱え込む
言いたいことを我慢し続けると、心の中にストレスや不満が蓄積されていきます。表面上は穏やかに見えても、内心では常に葛藤を抱えている状態となり、精神的な負担が大きくなります。

顔はにこにこしていて「いい人だね」って言われても、心は疲れてるんですよね。
長期間続くと、不安や抑うつ状態につながる可能性もあり、心身の健康に深刻な影響を与えかねません。
自己肯定感や自信の低下
自分の意見を言わない状況が続くと「自分の考えには価値がない」という思い込みが強化されてしまいます。発言しないことで失敗は避けられますが、同時に成功体験も得られません。その結果、自己肯定感はさらに低下し、自信を失う悪循環におちいってしまい、より発言しにくい状態が生まれます。
自分の本心がわからなくなる
常に他人に合わせる生活を続けていると、自分が本当に何を思い、何を求めているのかがわからなくなってしまいます。

もはや自分が思っていることなのか、環境に思わされていることなのかわからなくなるときがあります。
自分の感情や意見を抑制し続けることで、内面の声に耳を傾ける習慣がなくなり、自己理解が浅くなります。結果的に、自分らしい人生を歩むうえで大きな障害となってしまうのです。
チャレンジや成長の機会を逃す
意見を言わないということは、新しいプロジェクトや責任ある仕事への参加機会を逃すことにつながります。積極的な発言や提案は、周囲からの評価や信頼を得る重要な要素です。発言を避け続けることで、キャリアアップや個人的な成長のチャンスを自ら手放してしまう可能性があります。
受け身になり、被害者意識が強まる
自分から行動を起こさず、常に他人の決定に従う姿勢が習慣化すると、物事を主体的にコントロールする感覚を失ってしまいます。うまくいかないことがあっても「自分は何も言えなかった」「決めたのは自分ではない」という被害者意識が強くなり、責任感や当事者意識が薄れてしまいます。

あとになってから、「本当はこう思ってたのに…」と言ってしまうこともありますよね。
問題点や新しいアイデアが表面化しない
現場で働く人や当事者だからこそ見える問題点や改善案があるにも関わらず、発言しないことでそれらが埋もれてしまいます。特にチームにおいては、多様な意見や新鮮なアイデアが改革や成長の原動力となるため、貴重な情報や提案が失われることは成長のチャンスを逃すことになります。

めっちゃいいアイディアが思いついても、間違っているのが怖くて、つい言わずに終わってしまいます。
チームや集団の信頼関係や生産性低下
メンバーが本音で話し合わないチームでは、表面的な合意しか得られず、深い信頼関係を築くことができません。問題が隠れたまま進行するため、あとで大きなトラブルに発展するリスクも高まります。結果として、チーム全体のパフォーマンスや生産性が低下し、目標達成が困難になるのです。
失敗や不祥事が表に出にくい
組織内で意見を言いにくい雰囲気があると、問題の報告や改善提案が上がってこなくなります。小さな問題が放置され、気づいたときには取り返しのつかない大きな失敗や不祥事に発展するリスクが高まります。
早期発見・早期対応の機会を失い、組織全体に大きなダメージを与える可能性があります。
自分の意見が言えないときの克服・改善方法6つ
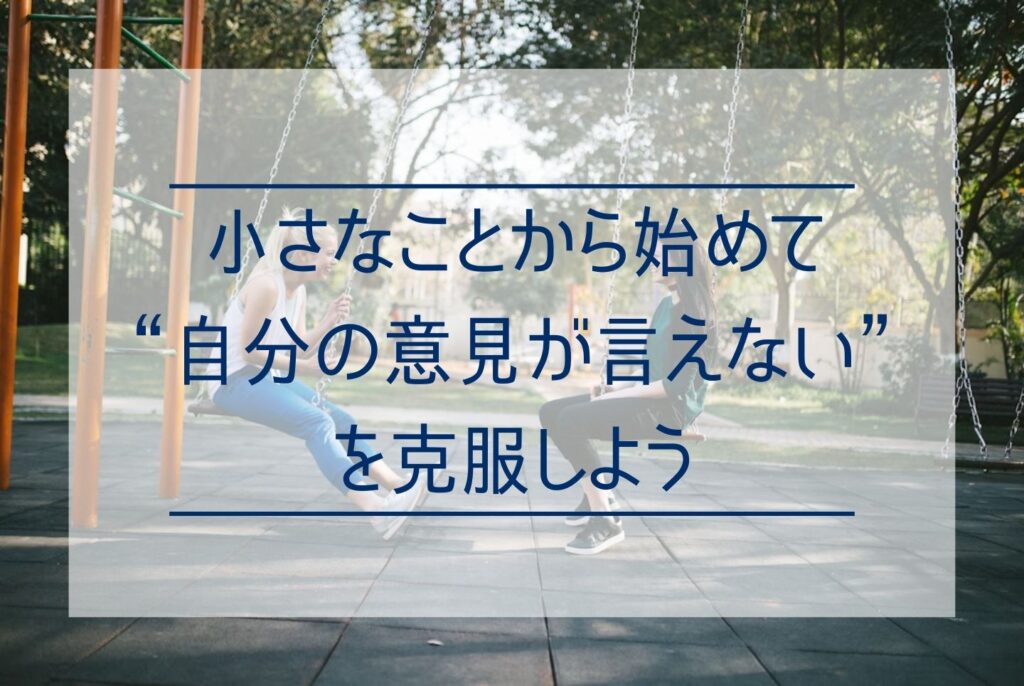
自分の意見が言えない悩みを解消するには、段階的にアプローチしていきましょう。一度に大きく変わろうとせず、小さなステップから始めることが大切です。ここでは、今日から実践できる6つの具体的な方法をご紹介します。自分に合った方法から取り組んでみてください。
自分の意見が言えないことを正直に話して良い
「実は自分の意見を言うのが苦手で…」と正直に周囲に伝えることから始めましょう。多くの人は、悩みを抱えていることに理解を示してくれるはずです。特に信頼できる家族や友人に打ち明けることで安心感が感じられ、発言しやすい雰囲気を作ってもらえます。

頑張って話す前に、まずは自分の本来の姿を認めて、開示することが大事です。
完璧を求めず、苦手なことを認めることは恥ずかしいことではありません。むしろ、素直に話すことで周囲のサポートを得やすくなります。
小さなことから意見を言う練習をする
いきなり重要な場面で発言するのではなく、日常のささいなことから意見を言う練習を始めましょう。

最初はドキドキするかもしれませんが、変わりたいのであれば少しずつチャレンジしてみてくださいね。
家族との会話、友人とのやりとり、お店での注文といった日常の場面で、少しずつ自分の意見を表現する習慣をつけていきましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、自信がついて発言への抵抗感が徐々に減っていきます。
言いたいことを紙に書き出してみる
頭の中で考えているだけでは整理がつかないことも、紙に書き出すことで明確になります。まず「なぜそう思うのか」「どう伝えたいのか」を文字にして整理してみましょう。書くことで自分の考えが客観視でき、論理的に組み立てられます。

まずは形式にとらわれずに、思ったことや考えていることをそのまま書き出してOKです!
他人に見られないノートやメモアプリなど、安心できる環境で取り組みましょう。紙に書き出して練習することで、自分の意見や感情が明確になります。また、言葉にする感覚がつかめるため、自分の意見を伝える力を養ううえで効果的です。
話しやすい環境や相手を選ぶ
すべての場面で意見を言う必要はありません。まずは話しやすい相手や環境を選んで練習することが大切です。理解のある上司、親しい同僚、家族など、あなたを受け入れてくれる人との会話から始めましょう。

「この人なら安心して自分のことを話せる」っていう人、いますよね。そういう人が1人でもいると、安心感は全然違います。
また、人数の少ない場面や、リラックスできる環境を選ぶことも重要です。無理をして苦手な状況に飛び込む必要はなく、段階的に慣れていくことで自然と発言できる場面が増えていきます。環境選びも立派なスキルのひとつです。
開き直って失敗を恐れない
「失敗してもいい」「完璧でなくてもいい」と開き直ることも重要な心構えです。

僕も開き直りは、すごく大事にしています。苦しい場面から開き直れたときって、人として一皮むけた感覚があるんですよね。
開き直るコツは、“最悪を想定して「それでも良いや」”と受け入れることです。
多くの人は失敗や批判を恐れて発言を控えますが、実際には思っているほど周囲は気にしていないものです。もし間違った発言をしても「勉強になりました」「次は気をつけます」と素直に受け入れれば良いのです。
失敗は成長の材料であり、完璧な人などいません。むしろ、開き直って失敗を恐れずに挑戦する姿の方が、周囲からの評価も高くなることが多いのです。
カウンセリングや相談を活用する
一人で悩み続けずに、専門家の力を借りることも有効な方法です。カウンセラーや心理士は、あなたの状況を客観的に分析し、具体的なアドバイスをしてくれます。

カウンセラーは、どんな話でもしっかりと受け止めてくれるプロです。安心して話せることが多いです。
また、職場の相談窓口や地域の相談センターなど、身近な相談先を活用するのもおすすめです。第三者の視点から問題を整理することで、新たな気づきや解決策が見つかることもあります。一人で抱え込まず、適切なサポートを受けながら自分の意見を出していくのがポイントです。
自分の意見を言えない人への接し方・関わり方のポイント
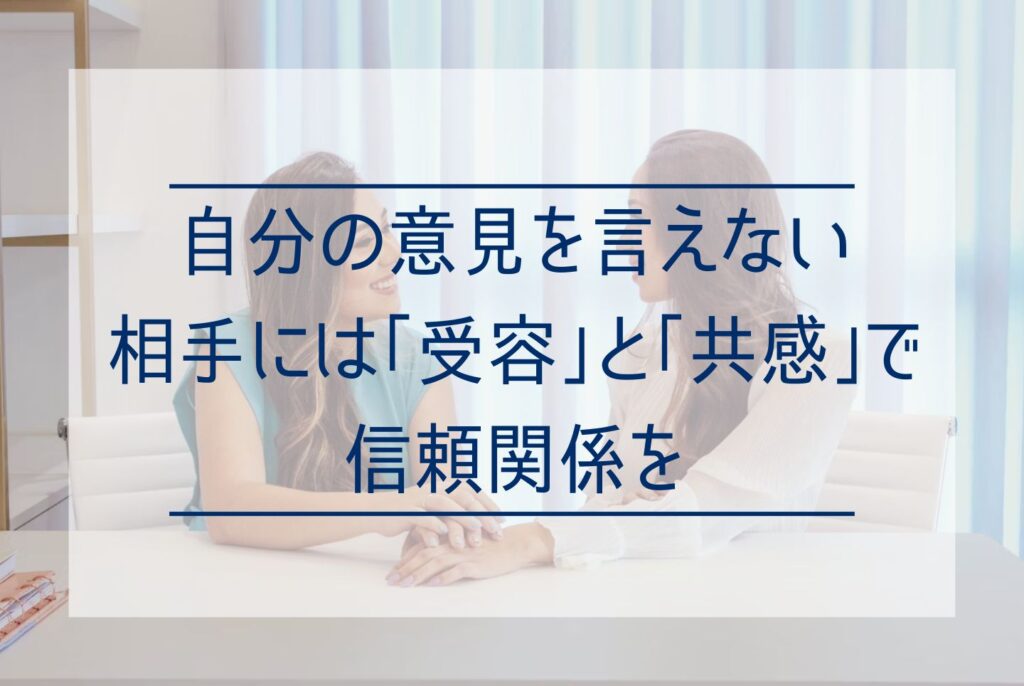
自分の意見が言えない人の周りにいる方にとって、どう接すれば良いかわからないことも多いでしょう。相手を変えることはできませんが、接し方を工夫することで発言しやすい環境を作ることができます。ここでは具体的なサポート方法をご紹介します。
「あなたの意見を聞きたい」をはっきり伝える
自分の意見が言えない人は「求められていない」と感じていることが多いため、明確に意見を求めていることを伝えましょう。「〇〇さんはどう思いますか?」「あなたの考えを教えてください」といった直接的な問いかけが効果的です。

むずかしいですが、できるだけ「あなたを受け入れている」という雰囲気や表現が大事ですね。
曖昧な表現ではなく、はっきりと意見を求めることで発言のきっかけを作れます。相手は勇気を出して話してくれようとしています。聴くときは、上記のような相手を受け入れる雰囲気や表現を大事にしましょう。
「イエス・ノー」で答えやすい質問を意識する
いきなり「どう思う?」と聞かれても答えにくい場合があります。「この案について賛成ですか?」「Aプランの方が良いと思いますか?」のように、選択肢を示した質問から始めましょう。答えやすい形式で質問することで、まずは発言のハードルを下げ、少しずつ詳しい意見を聞き出せます。

「イエス・ノー」で答えられる質問から、「なぜそう思いますか?」「理由を教えてもらえますか?」といったオープンクエスチョンにつなげるとスムーズです。
肯定的なリアクションは共感はもちろん、なかなか詳しい回答が返ってこない時間もあるでしょう。焦らず相手のペースに合わせて、ゆっくり説明できる安心感を与えることも大切です。
相手の興味や好きなことに沿って質問する
相手が関心を持っている分野や得意なことについて質問すると、自然と発言しやすくなります。趣味や専門知識、過去の経験など、相手が話しやすいトピックから入ることで緊張がほぐれ、意見を言うことへの抵抗感が和らぎます。

誰でも何かには興味があるはずです。興味のあることを好きに話して良いなら、喜んで話してくれるかもしれませんね。
相手をよく観察し、興味のあることを把握しておくことが大切です。興味や好きなことに沿って会話をしていくうちに、信頼関係も深まります。信頼がおける相手には、少しずつ自分の本当の思いや意見を言いやすくなるものです。
どんな意見でも否定をせずにしっかり聴く
せっかく勇気を出して発言した意見を否定されると、次回から話すことが怖くなってしまいます。

もともと自信がなくて勇気をもって話したのに、否定されると「もう二度と話したくない」って思いますよね。
異なる意見であっても、最初は聴く姿勢に徹することが重要です。
「なるほど」「そういう見方もありますね」と、まずは受け止める姿勢を示しましょう。自分の価値観と異なる話題が出ると、つい「でもそれは…」と口をはさみそうになりますが、「今は相手に話してもらう時間」と傾聴に徹しましょう。

安心して話せる相手だと認識してもらうことが第一歩ですね。
「意見が言えない」ことを長所として捉える
「意見が言えない=ネガティブ」というイメージをもつ人も少なくないでしょう。ただ、自分の意見を言えないことは、本当にネガティブなことだけなのでしょうか。

実は、次のようなメリットもあると思います。
自分の意見が言えない人は、慎重で思慮深く、相手の気持ちを考えられる優しさをもっています。「よく考えてから話すから信頼できる」「みんなの意見をよく聞いてくれる」といった長所に注目し、特性を活かせる場面を作ることで、自信を持って発言できるようになっていきます。
「自分の意見が言えない」を克服して、自分らしい人生を歩む
本記事では、次のような方に対して、自分の意見が言えない原因や対処法について解説しました。
記事のポイントは、次の通りでした。
自分の意見が言えない状況は、心理面と環境面の複合的な要因によって生まれますが、適切なアプローチで少しずつ、でも確実に改善できます。小さな一歩から始めて、自分の意見を言う力を身につけていきましょう。

最初は勇気がいるかもしれません。でも、不安や怖さを乗り越えた先には成長した自分がいるはずです。
あなたの声には価値があります。心に素直になり、自分らしい人生を歩んでいってください。
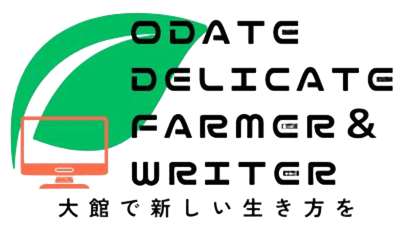
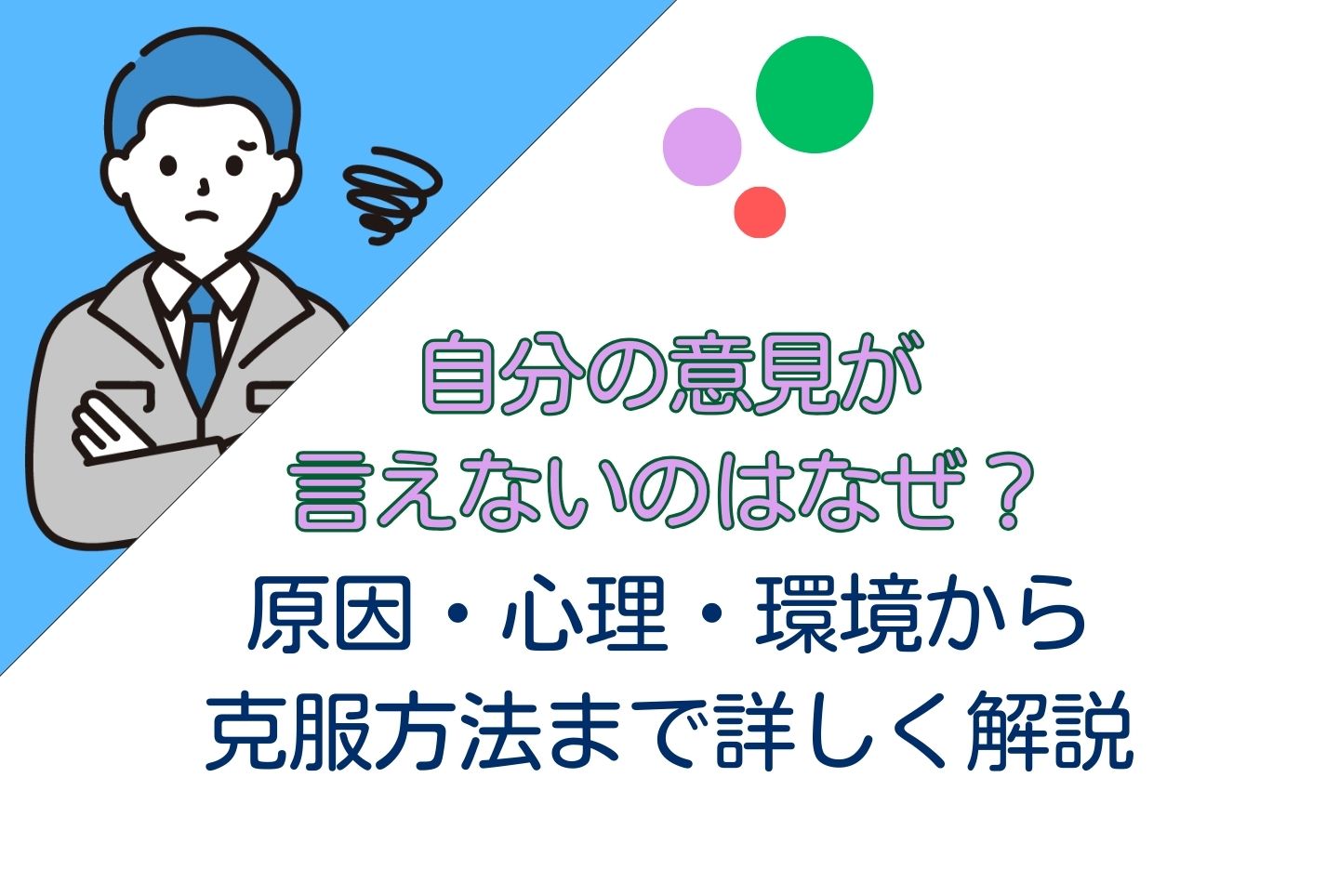

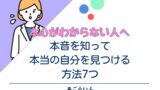


コメント